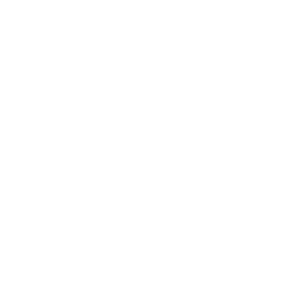火山列島の日本では、さまざまな山が各地に聳え立ち、人だけではなくさまざまな命を育むまさに大地の母といった存在だ。白山信仰においても水分の神様(水を分け与える神様)としての信仰があるように、雨水や溶け出す雪が大地に染み込み、山から海にかけた広範囲で水の恩恵をさまざまな動植物が受けている。
そんないのちを支え続ける恵の山はかつてより神域として人は関わってきた。また、空に近い山の存在は“あの世”に近い場所と考えられており、登拝することで浄化したり亡くなった方を成仏する願いを行う聖域であった。
この世(現世)とあの世(黄泉の世界)を行き来する境として、白山の地域は白山登拝前最後の人の暮らしがあった場所であり、そこには馬場(ばんば)と呼ばれる馬をつなぎとめておいた場所があった。
異なる2世界のあわいの存在として、「三途の川」という言葉を聞いたことがあるのではないだろうか?神社にある「しめ縄」は、外からの不浄な物を神聖へ触れさせないための外界の境界線であったり、境内にある「橋」などもそのような意味を持っていることがある。
白山信仰においては加賀、越前、美濃の3つの禅定道(ぜんじょうどう)に馬場が設けられていた。美濃馬場は現在の長滝白山神社にあった。

白山登拝前、長滝白山神社までの禅定道の道のりは馬を使って白山を目指すことが可能であったが、長滝白山神社以北の神域では下馬下乗での登拝となり、登拝中に馬を預ける場所であった。
また、時代が経ち、白山信仰が大衆化すると馬場は修験者の「行場」としての意味を持ち、お経を唱えたり、説教を受けたりと、入山の準備として心身を浄める場所として、多くの人で賑わったと言われる。
山の尾根沿いにあったと言われる古道(かつての道)と現在の鉄道や国道、高速道路の道は異なるが、長良川に沿った地形で共に南北に長い道のりだ。
八幡、大和から白鳥、高鷲へ北上する際は、長滝白山神社へお立ち寄りいただき、一度手を合わせてみていただきたい。白山の恵みに感謝し、白山を目指した人たちの思いを感じることができるかもしれない。